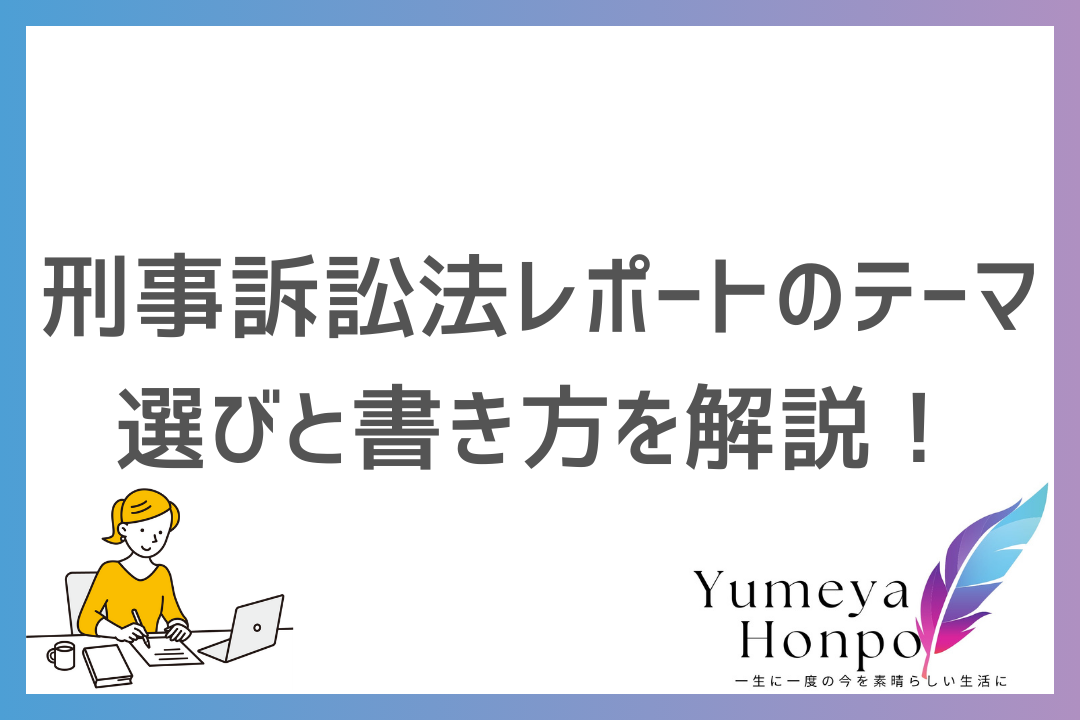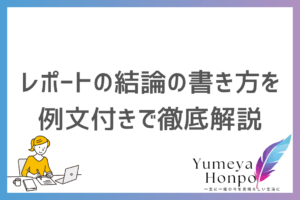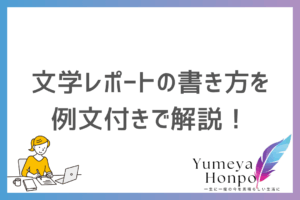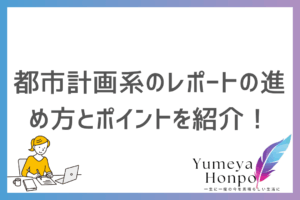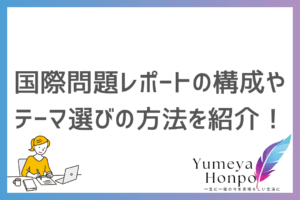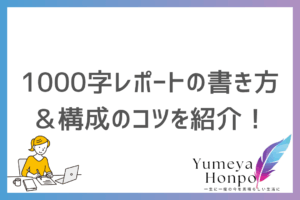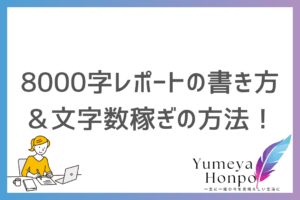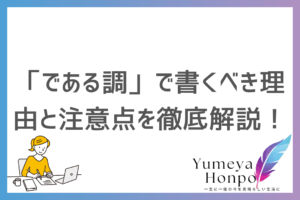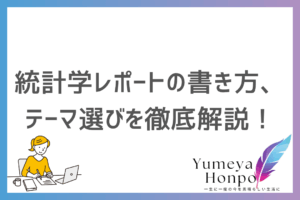「刑事訴訟法レポートって、どんなことを書いたらいいの?」
「テーマはどうやって決めたらいい?」
「判例は書いた方がいい?」
刑事訴訟法レポートを作成する時に、テーマ選びや構成に悩む学生は多いのではないでしょうか。
刑事訴訟法レポートは、法律のルールや判例をもとに書く必要があります。
この記事では、刑事訴訟法レポートの書き方について、テーマ選びから判例の活用方法まで、わかりやすく解説していきます。
刑事訴訟法のレポートをプロに代わりに書いてもらいたい方はこちら
刑事訴訟法レポートのテーマ選び

刑事訴訟法レポートを書く際、何を題材にすればいいか悩んでしまう人は少なくありません。
ここでは、テーマを探すときのコツを2つ紹介します。
裁判傍聴やドラマ
ドラマやニュースを見たり、裁判傍聴したりすることで、レポートのテーマの取っ掛かりを得られます。
例えば、防犯カメラの映像がニュースやドラマでよく取り上げられています。
しかし、その撮影や使用にはプライバシー保護があり、刑事訴訟法では証拠の取り扱いに注意が必要です。
そこに違法収集証拠排除法則(違法な手段で収集された証拠は、原則として裁判で証拠として使用できないとするルール)などを絡めることで、レポートとして書けます。
また、参考文献や判例が多いほどレポートが書きやすくなるので、テーマを決める前に判例がどれくらいあるかも調べておきましょう。
身近な操作
刑事手続の一部である捜査は、意外と身近なところで行われています。
例えば、所持品検査は職務質問と一緒に行われることがあり、警察官職務執行法第2条1項に関係しています。
警察官職務執行法第2条1項の規定は以下の通りです。
警察官職務執行法第2条1項:「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」
所持品検査は職務質問と似ており、任意で行われていますが、どこまでが適法でどこからが違法になるのかは明確ではありません。
このような身近な経験を題材にすることで、テーマを見つけやすくなります。
刑事訴訟法の重要なポイント

レポートを書く際は、刑事訴訟法の考え方をしっかりと押さえることが大切です。
その中でも基礎となる「法的三段論法」と「判例」について説明します。
法的三段論法
法律学で物事を考える際には、法的三段論法を使います。
法的三段論法とは、「大前提」と「小前提」から「結論」を出すという方法です。
例えば、窃盗罪を題材にすると次のようになります。
大前提:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条、窃盗罪)
小前提:AはBの鞄を盗んだ
結論:Aは10年以下の懲役または50万円以下の罰金
このように、規範に当てはめていくことでさまざまな問題を応用できます。
判例の活用方法
判決も、この法的三段論法の流れに沿って書かれています。
特に最高裁判所の判決は判例と呼ばれ、その中で示された法律の解釈やルールは、法律の条文と同じくらい重要です。
そのため、レポートを書く際には、テーマに関連する判例を参考にしましょう。
判例は、裁判所の公式サイトや図書館で無料で閲覧できるほか、有料の判例データベースを使えば効率的に探すことができます。
判例を使うときは、内容をよく理解し自分の意見とどうつながるか説明することで、質の高いレポートになります。
レポートの進め方

刑事訴訟法レポートの構成とその進め方を紹介します。
以下の順番でレポートを書き進めるようにしてください。
序論(導入)
序論では、数ある刑事訴訟法のテーマから、そのテーマを選んだ理由を書きます。
「○○は近年取り上げられることが多い~」のように昨今の話題と絡められると、レポートの評価も上がりやすいです。
また、これから述べる内容についても簡単に触れておきましょう。
例文:近年、防犯カメラは街中のいたるところに設置され、犯罪捜査において重要な役割を果たしている。コンビニ強盗事件や交通事故の解決に防犯カメラの映像が決め手となったニュースを目にすることも多い。しかし、防犯カメラによる撮影は市民のプライバシーを侵害する可能性があり、その映像を証拠として使用することには慎重な検討が必要である。では、防犯カメラの映像はどのような場合に適法な証拠として認められるのだろうか。本レポートでは、違法収集証拠排除法則の観点から防犯カメラ映像の証拠能力について検討する。
本論
本論では、法的三段論法を使って書き進めます。
最初に規範を示し、関連する条文や判例を挙げましょう。
そのうえで、自分の意見や考察を加えると、まとまりのある質の高いレポートになります。
例文:防犯カメラ映像の証拠能力を判断するには、まず撮影行為の適法性を検討する必要がある。最高裁昭和44年12月24日判決(京都府学連事件)によれば、「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」が憲法13条により保障されている。
しかし、すべての撮影が違法となるわけではない。同判決は、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性と緊急性があり、かつ相当な方法で行われるときは、令状なくして撮影することが許容されるとしている。防犯カメラの場合、設置場所や撮影範囲によって適法性の判断が変わってくる。公道や商業施設など公共性の高い場所での撮影は、プライバシーの期待が低いため比較的認められやすい。一方で、住宅地や私有地を過度に撮影する場合は、プライバシー侵害の程度が高くなり、違法とされる可能性がある。仮に撮影行為が違法であった場合、その映像は違法収集証拠として証拠能力が否定される可能性がある。最高裁昭和53年9月7日判決によれば、証拠物の収集手続きに令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められる場合には、証拠能力が否定されるとしている。
結論
導入で書いた問題点への答えや結果をまとめましょう。
今後の課題や展望についても書くと良いです。
例文:防犯カメラ映像の証拠能力は、撮影の適法性によって決まる。撮影場所の公共性、犯罪の現行性、証拠保全の必要性などを総合的に判断し、プライバシー権との適切なバランスが保たれている場合に証拠として認められる。違法な撮影による映像は、違法収集証拠排除法則により証拠能力を否定される可能性がある。
そのため、防犯カメラ映像を証拠として使用したい場合は~~~(略)
(今後、防犯カメラ技術の発展に伴い、より精緻な法的基準の確立が求められるだろう。)
参考文献
他のレポートと同様に、引用箇所や参考文献は必ず明記してください。
記載がないと剽窃にあたります。
刑事訴訟法の条文を引用する場合は何条かを明記し、判例も同様に記載します。
レポート作成に困ったら

刑事訴訟法レポートは、テーマ選びから判例や条文の調査までやることが多く、思うように書き進められない方も多いでしょう。
時間がない、うまく書けないと感じたら、レポート代行サービスを利用するのも一つの方法です。
夢屋本舗では、幅広い分野に対応しており、刑事訴訟法レポートの作成も依頼できます。
法的三段論法を用い、判例や条文を参考にして質の高いレポートを作成してくれます。
大学生向けのレポート代行業者を比較した記事がありますので、迷っている方はぜひ読んでみてください。
まとめ
この記事で解説した内容をまとめると以下の通りです。
- テーマ選び:裁判傍聴やドラマ、身近な操作
- 刑事訴訟法の重要なポイント:法的三段論法、判例の活用方法
- レポート作成の進め方:序論(導入)、本論、結論、参考文献
- レポート作成に困ったとき:夢屋本舗のようなレポート代行サービスを利用
上記の内容を参考にすることで、刑事訴訟法レポートが書きやすくなります。
とはいえ、テーマ選びや判例調べに時間がかかるものです。
そんなときは、夢屋本舗のようなレポート代行サービスを活用することで、高品質なレポートが提出できるだけでなく、他の課題やアルバイトに時間を使うことができます。