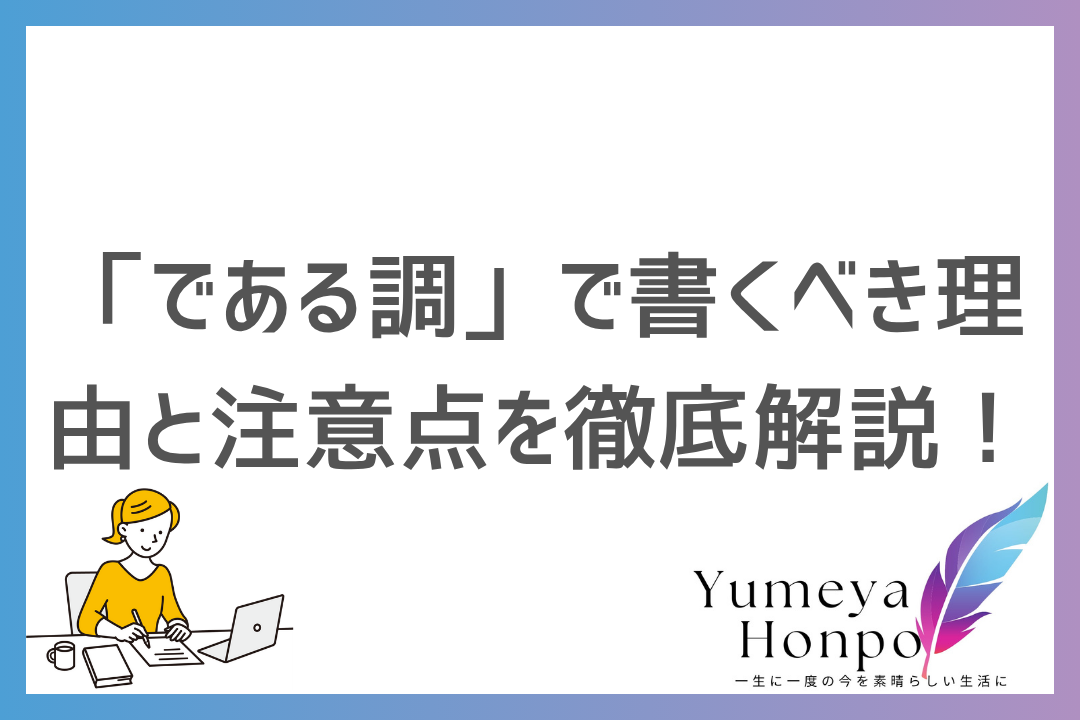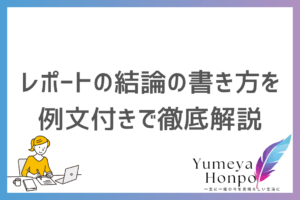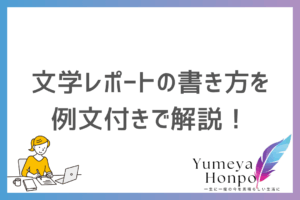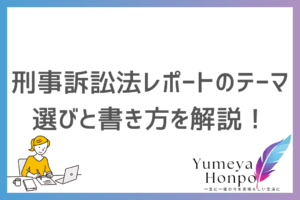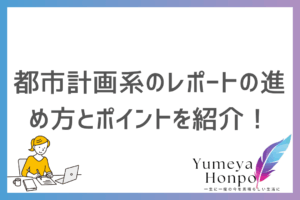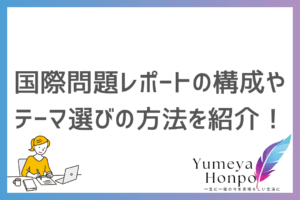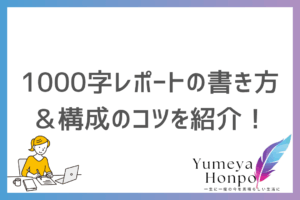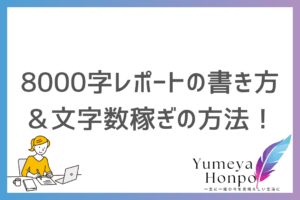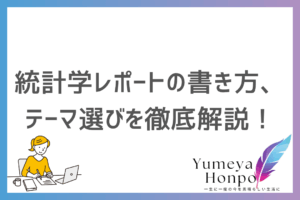「レポートの文体は『である調』と『ですます調』のどっちを使えばいいの?」
「文体がつい混ざってしまう…」
「教授に良い印象を与える文体の使い方を知りたい」
大学生になって初めてレポートを書く時、多くの人が悩むのが文体の選び方です。
高校までの作文では「ですます調」で書いていたのに、大学のレポートでは「である調」が良いと言われて戸惑った経験はありませんか?
実は、レポートの文体選びには明確なルールがあり、適切な文体を使うことで評価が変わることがあります。
この記事では、レポートの文体について、使い分けの基準から実践的なテクニックまで、以下の内容で詳しく解説していきます。
レポートを取り組む時間がない、レポートの書き方がまだわかっていないからレポート代行を頼みたいという方はこちら
レポートでは「である調」が基本!その理由を解説

大学のレポートでは、基本的に「である調」を使用することが一般的です。
しかし、なぜ「である調」が良いのか、その理由をきちんと理解している学生は意外と少ないです。
学術的文章としての説得力
レポートは論理的に自分の考えを述べ、教授などの読み手に納得してもらうことを目的としています。
「である調」は断定的で簡潔な表現ができるため、説得力のある文章を書きやすくなります。
文字数を減らせる
レポートには文字数制限があることが多く、限られた文字数の中で内容を充実させる必要があります。
「ですます調」は丁寧な表現である反面、語尾が長くなりがちです。
3000字のレポートで「ですます調」を使うと、語尾だけで150〜250字を使ってしまうこともあります。
一方、「である調」なら同じ内容をより少ない文字数で表現でき、その分、本文や具体例に文字数を割くことができます。
教授からの評価への影響
大学のレポートは、「である調」で書くことが前提とされています。
これは学術論文や専門書がすべて「である調」で書かれているためで、学生にも同じ文体での執筆を求めています。
「ですます調」を使用することで減点されることはないかもしれませんが、特に指定がないなら「である調」を使いましょう。
レポートを書く際は文体の他にも様々な制限があるため、面倒な方はレポート代行の利用がおすすめです。
文体を使い分ける場面
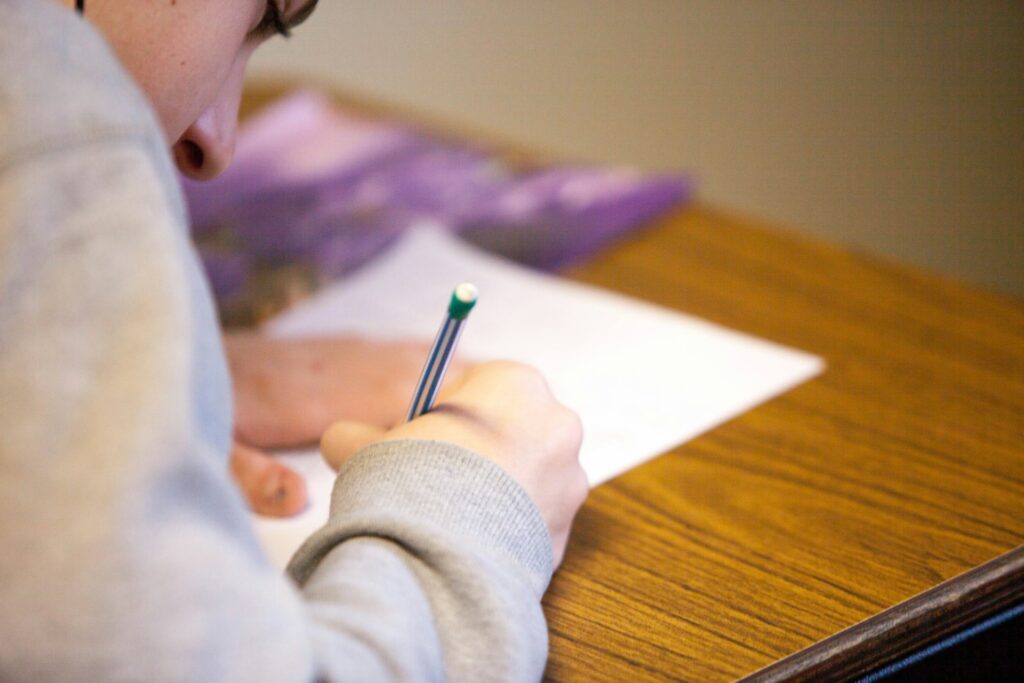
多くのレポートは「である調」で書きますが、大学のすべての課題に当てはまるわけではありません。
状況に応じて適切に使い分けるようにしましょう。
分野によって文体を使い分ける
分野によっても、文体の扱いに違いがあります。
理系分野では、ほぼ「である調」が使用されます。
実験結果や数式の説明には、客観的で簡潔な表現が求められるためです。
文系分野でも基本的には「である調」ですが、教育学や心理学の一部では、読み手への配慮から「ですます調」を使用することもあります。
「である調」を上手に使うテクニック
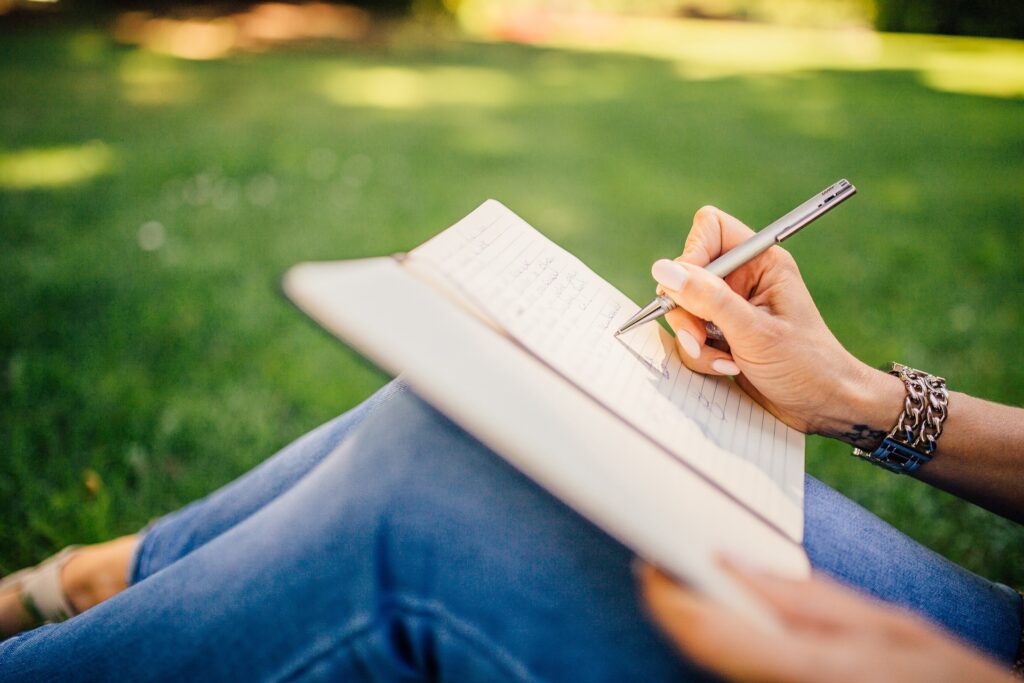
「である調」に慣れていない人でも、以下のようなテクニックを押さえれば、自然な文章が書けるようになります。
語尾のバリエーションを増やす
「である調」というと「〜である」ばかり使ってしまいがちですが、実は様々な語尾があります。
以下の語尾を使い分けると、文章に自然な流れが生まれます。
- 「〜だ」:最も基本的な断定表現
- 「〜といえる」:やや控えめな断定
- 「〜と考えられる」:推測を含む表現
- 「〜ことがわかる」:結果や発見を示す
- 「〜必要がある」:提案や主張を示す
これらを使い分けることで、単調でない読みやすい文章になります。
主語と述語の関係を明確にする
である調では文が短くなりがちなので、主語と述語の関係を明確にするようにしましょう。
以下の例のように、主語と述語をはっきりさせることで、教授に伝わりやすい文章になります。
- 曖昧な例:「問題が複雑化している。解決が困難である。」
- 明確な例:「環境問題が複雑化している。そのため、単一のアプローチでの解決は困難である。」
主語を明示し、文と文のつながりを明確にすることで、論理的で理解しやすくなります。
文体の注意点
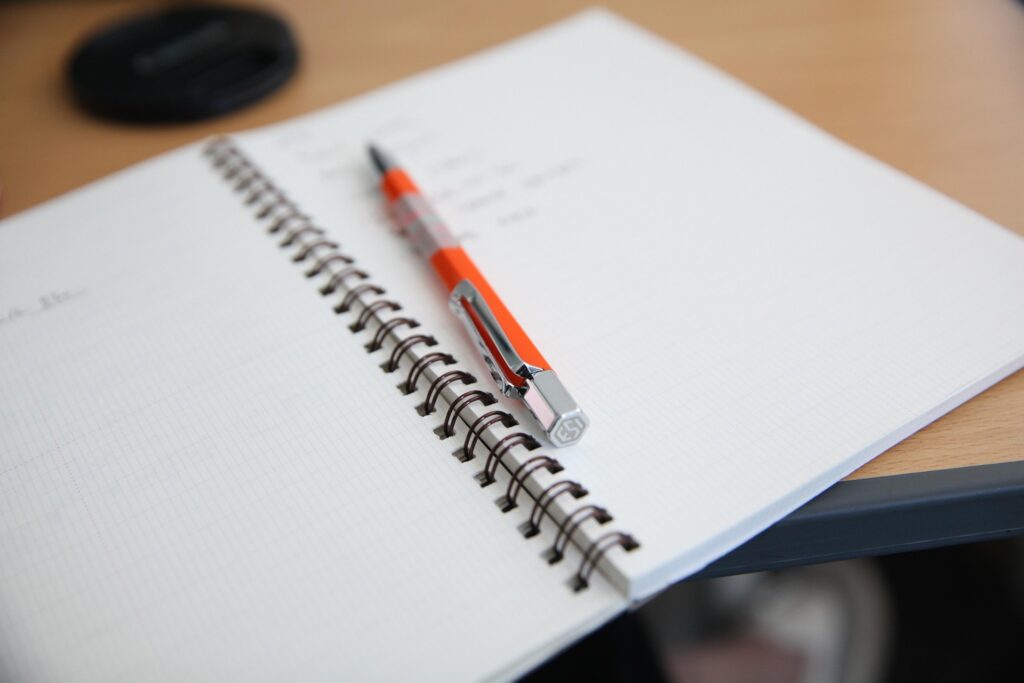
レポートを書く際に、多くの学生が陥りやすい文体の間違いがあります。
以下のようなことに注意しましょう。
文体の混在を避ける
最もよくある間違いは、「である調」と「ですます調」が混在してしまうことです。
これは特に長いレポートを書いている時に起こりやすく、レポートの質を下げてしまいます。
対処法として、以下の方法が有効です。
- 下書きの段階で文体を決める
- 各段落の最初と最後の文を特に注意して確認
- 提出前に音読して違和感がないかチェック
- 文章作成ソフトの検索機能で「です」「ます」を検索
話し言葉の混入に注意
である調で書いていても、つい話し言葉が混じってしまうことがあります。
以下の表現には注意してください。
- 「〜かもしれない」→「〜可能性がある」
- 「〜と思う」→「〜と考える」「〜と推測される」
- 「でも」→「しかし」「ただし」
- 「だから」→「したがって」「そのため」
レポートなどの学術的な文章では、より客観的な表現を使うよう心がけましょう。
文体以外の仕上げチェックポイント
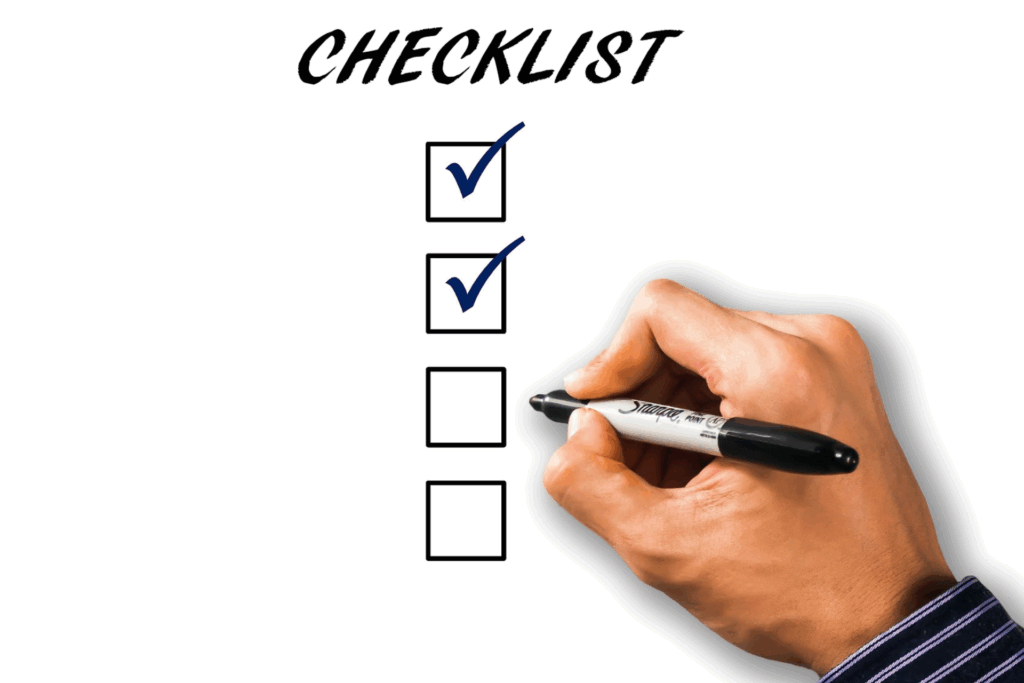
レポートを仕上げるには、文体だけでなく以下のような項目もチェックしましょう。
4つのチェックポイント
レポートを書き終えたら、必ず以下のポイントを元に推敲を行いましょう。
- 文体の統一性(である調で統一されているか)
- 語尾の重複(同じ語尾が連続していないか)
- 文の長さ(一文が長すぎないか)
- 専門用語の説明(初出時に説明があるか)
時間を置いてから読み返すと、書いている時には気づかなかった問題点が見つかることがあります。
レポートが書けない時の対処法

初めてのレポートでは「である調」で書くことに苦労する学生も少なくありません。
時間がない、どうしても上手く書けないという場合は、レポート代行サービスを利用するのも一つの選択肢です。
特に夢屋本舗は、他のレポート代行業者よりも料金体系が明確で、文字数が増えるほど文字単価は下がるので安心してご依頼いただけます。
大学生向けのレポート代行業者3社の比較を行いましたので、レポート代行を利用したいと考えている方はぜひご覧ください。
まとめ
レポートの文体選びは、レポートを書くうえで最初に直面する課題です。
この記事で解説した内容をまとめると、以下のようになります。
- 基本的な文体:大学のレポートでは「である調」が基本で、説得力と効率性の観点から推奨される
- 使い分けの基準:多くのレポートは「である調」だが、課題の指示を確認することが重要
- である調のテクニック:語尾のバリエーション、主語と述語の明確化で読みやすい文章に
- 文体の注意点:文体の混在、話し言葉の混入
- 仕上げチェックポイント:文体の統一性、語尾の重複、文の長さ、専門用語の説明
- 書けない時の対処法:夢屋本舗のようなレポート代行を利用
適切な文体を使いこなすことで、レポートの質は確実に向上します。
最初は難しく感じるかもしれませんが、レポートを大量に書いていくことで上達します。
そもそもレポートの作成自体に困っている場合は、プロの力を借りることで、時間を有効活用しながら質の高いレポートを提出することができるでしょう。