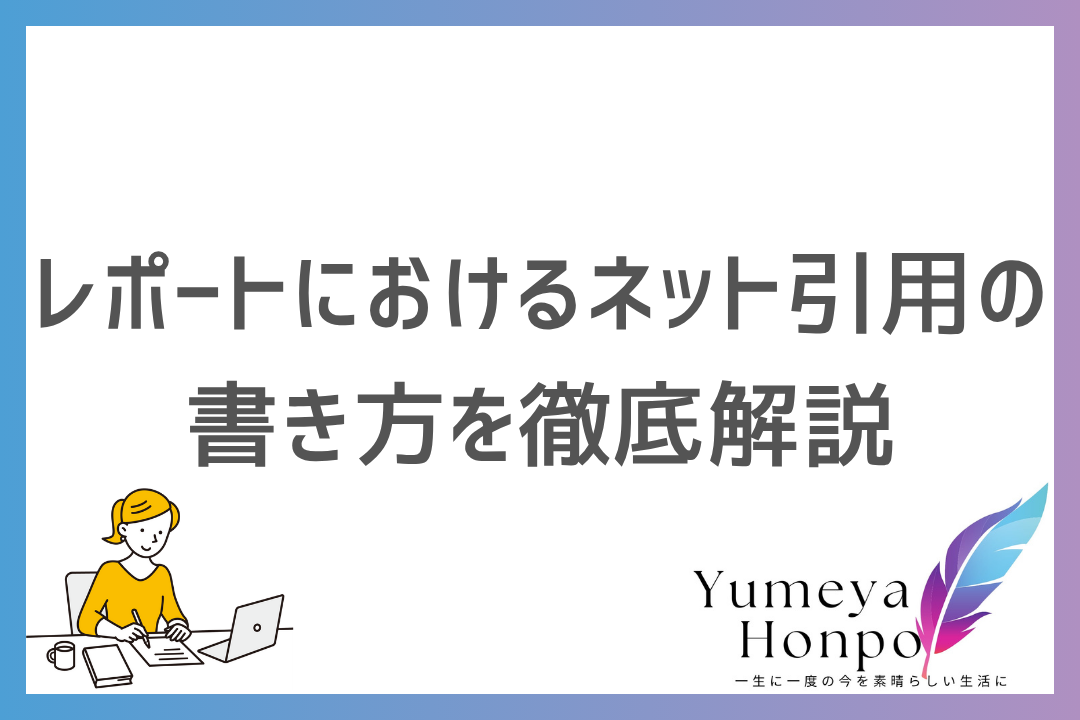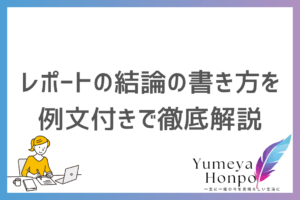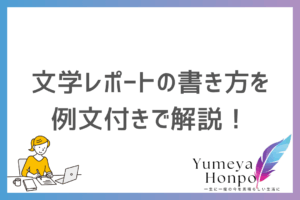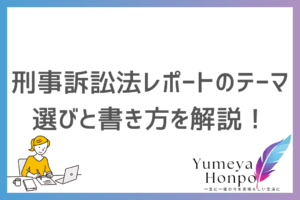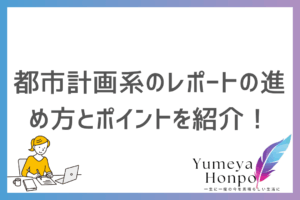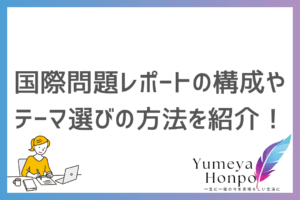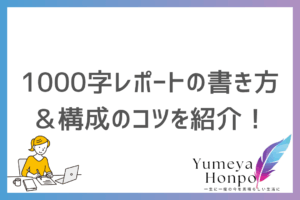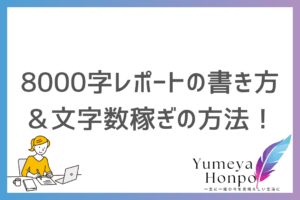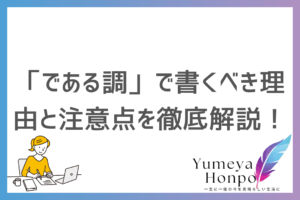「参考文献の書き方がわからない」
「どこから引用したらいいの?」
「参考文献を書くうえで注意することは?」
大学でレポートを書く際に、インターネットの情報を活用する場面は非常に多くあります。
しかし、「ネットの情報をどう引用すればよいのか」「どんなサイトなら引用してもよいのか」といった疑問を持つ学生は多いでしょう。
適切な引用方法を身につけることで、質の高いレポートを作成できるようになります。
この記事では、レポートでネット上の情報を正しく引用する方法について、具体例を交えながら解説します。
ネット引用で気を付けるべき3つの基本原則

ネットから引用する際は、以下の3つの点に注意しましょう。
1. 信頼できる情報源を選ぶ
レポートの情報源には、引用しても大丈夫な情報源と避けるべき情報源があります。
引用しても大丈夫な情報源
- 学術論文データベース(CiNii、J-STAGE、Google Scholar等)
- 政府・公的機関のウェブサイト
- 企業・団体の公式サイト
- 大学・研究機関の公開資料
- 新聞社の記事データベース
引用を避けるべき情報源
- Wikipedia(第三者が自由に編集可能)
- 個人ブログ(情報の正確性が保証されない)
- まとめサイト(出典が不明確)
- SNSの投稿(一次情報源ではない)
Wikipediaやまとめサイトなどは簡単に情報を収集できますが、適切な内容が書かれているわけではないので、引用しないようにしましょう。
2. 著者と発行日を確認する
信頼できる情報源であっても、以下の情報が明記されているか確認します。
- 著者名または発行機関名
- 公開日または最終更新日
- 記事やページのタイトル
これらの情報が不明な場合は、信頼度が落ちるため注意が必要です。
3. 最終閲覧日を記録する
ウェブ上の情報は更新や削除される可能性があるため、必ず閲覧した日付を記録しましょう。
これにより、「少なくともその時点では存在した情報である」ということを示すことができます。
レポートの引用文献にはこのような注意点があります。
これらが面倒で誰かにレポートを作成してもらいたいと思ったなら、レポート代行サービスがおすすめです。
文中での引用表示方法

引用には「直接引用」と「間接引用」があり、それぞれ書き方が違います。
それぞれ正しい方法を紹介します。
1. 直接引用の場合
原文をそのまま引用する場合は、以下のように表記します。
短い引用(40字程度)の場合
山田(2023)は「デジタル化の進展により、情報リテラシーの重要性が増している」¹と指摘している。
長い引用の場合
田中(2024)は以下のように述べている。
デジタル技術の発展は、私たちの学習環境を大きく変えました。
特に、オンライン上の学術情報へのアクセスが容易になったことで、
研究や学習の可能性が大きく広がっています²。
2. 間接引用(要約・言い換え)の場合
間接引用とは、他者の意見や論文の内容を、自分の言葉で要約したり言い換えたりする方法です。
間接引用をする場合は、以下のように引用しましょう。
近年の研究では、適切な情報源の選択がレポートの質を左右することが明らかになっている(佐藤 2023)³。
参考文献(引用元)の書き方
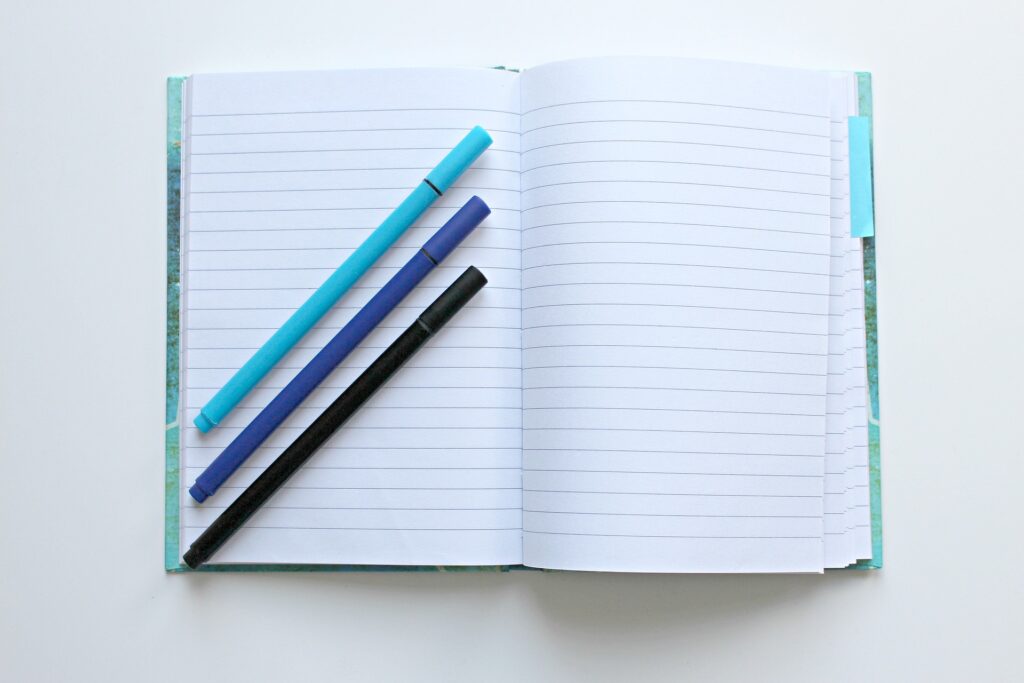
引用した参考文献は、レポートの最後にまとめて記載する必要があります。
ここでは、参考文献の書き方を紹介します。
1. 基本的な記載方法
学術論文と一般的なウェブサイトでは、引用の書き方に少し違いがあります。
学術論文の場合
[1] 著者名(発行年)「論文タイトル」『掲載誌名』巻号, pp.開始頁-終了頁, URL, (最終閲覧日:yyyy/mm/dd)
例:
[1] 鈴木太郎(2023)「情報リテラシー教育の現状と課題」『教育学研究』90巻3号, pp.45-62,
https://example.com/article123, (最終閲覧日:2024/03/15)
ウェブサイトの場合
[2] 発行機関名(更新年)「ページタイトル」ウェブサイト名, URL, (最終閲覧日:yyyy/mm/dd)
例:
[2] 文部科学省(2024)「大学における情報教育の推進について」文部科学省ホームページ,
https://www.mext.go.jp/example, (最終閲覧日:2024/03/20)
2. 情報が不明な場合の対処法
サイトによっては、著者名や発行年が記載されていないことがあります。
その際は、以下の情報を代わりに書きましょう。
著者名が不明な場合
- 発行機関名を代わりに記載
- 機関名も不明なら、ページタイトルを「」で囲んで記載
発行年が不明な場合
- (n.d.)と記載(no dateの略)
- 最終更新日があればそれを使用
参考文献の探し方や記載の仕方については、以下の記事をご覧ください。
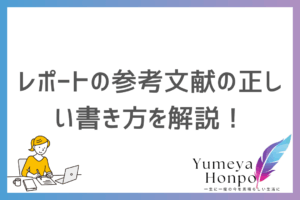
引用する際の注意点

参考文献の書き方を間違えると、減点の対象になることがあります。
また、引用表示なしに他者の文章を使用することは、剽窃(盗用)にもなってしまいます。
そのため、引用する際は以下のポイントに気をつけましょう。
1. URLだけの記載
ネット上の資料を引用する際にURLだけを記載すると、読者が情報を確認できないことがあります。
間違い例
[1] https://example.com/article123
正しい例
[1] 山田花子(2023)「研究倫理の基本」『大学教育研究』5巻, pp.12-25,
https://example.com/article123, (最終閲覧日:2024/03/25)
URLだけではなく、著者名から閲覧日まで全て書くようにしましょう。
2. 孫引き(二次資料からの引用)
孫引きとは、他の本や論文で引用されている内容を、自分のレポートなどに直接引用することです。
要は、原典を読まずに、他のレポートで引用されていた内容を引用することです。
本の中に引用されていた内容を使いたい場合は、できるだけ引用元の原典を自分で確認し、原典から直接引用するようにしましょう。
孫引きの例(望ましくない)
田中(2023)によると、山田は「デジタル化が進んでいる」と述べている。
※実際は田中の論文しか読んでいない
孫引きをする場合の正しい例
山田(2022)は「デジタル化が進んでいる」と述べている(田中 2023より引用)。
※孫引きであることを明記する
孫引きは原則として避けるべきですが、どうしても原典にアクセスできない場合には、上記のように孫引きであることを明示しましょう。
3. 複数の情報源を比較する
1つの情報源だけに頼るのではなく、複数の信頼できる情報を集めて比較することが大切です。
例えば、ある統計データについて論じる場合、省庁の公式データ、学術論文、信頼できる研究機関の報告書など、複数の情報源を確認することで、より説得力のあるレポートになります。
引用を含んだレポートを簡単に作成する方法

レポートを書くのに、どこから引用したらいいのかわからない、参考文献の探し方がわからないという場合は、レポート代行サービスを頼るのも一つの手段です。
夢屋本舗では、適切なサイトから引用し、参考文献まで含めた高品質なレポートを作成しています。
引用するための情報源が見つからず、レポート作成に悩んでいる方はぜひご利用ください。
大学生向けのレポート代行業者を徹底比較しましたので、レポート代行の利用を考えている方はご覧ください。
まとめ
ネット上の情報を引用する際は、「信頼できるサイトからの引用」「適切な引用表示」の2点が重要です。
まとめです。
- ネット引用の基本原則:信頼性の確認、著者と発行日を確認、最終閲覧日を記録
- 参考文献の書き方:
学術論文、著者名(発行年)「論文タイトル」『掲載誌名』巻号, pp.開始頁-終了頁, URL, (最終閲覧日:yyyy/mm/dd)
ウェブサイト、発行機関名(更新年)「ページタイトル」ウェブサイト名, URL, (最終閲覧日:yyyy/mm/dd) - よくある間違い:URLだけの記載、孫引き、複数の情報源を比較、剽窃に注意
最初は面倒に感じるかもしれませんが、正しい引用方法を身につけることで、レポート作成がスムーズになります。
とはいえ、引用先を探すのに時間がかかったり、信頼できる情報源がわからなかったりすることもあるでしょう。
そんな時は、夢屋本舗のようなレポート代行サービスに頼るのも一つの手段です。