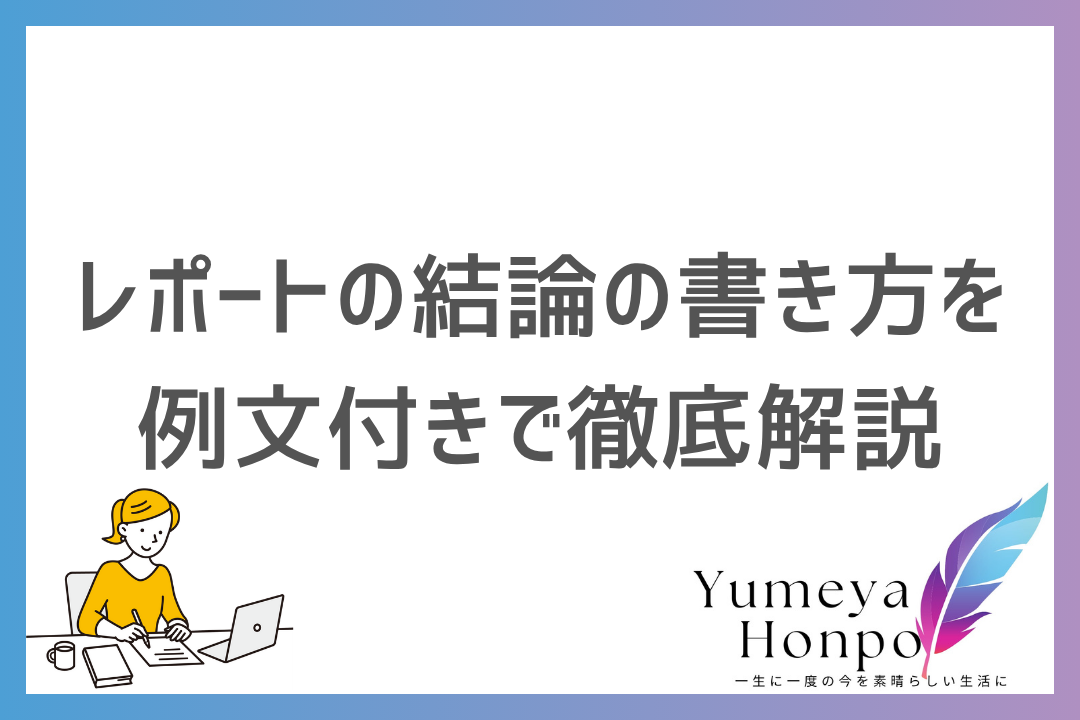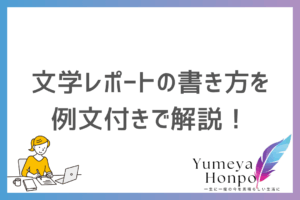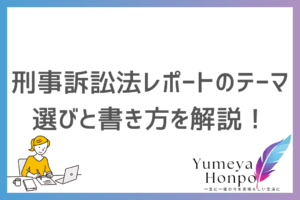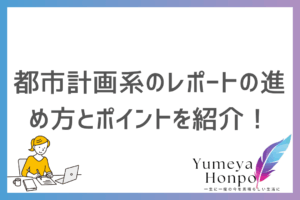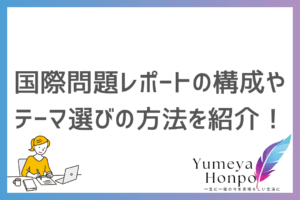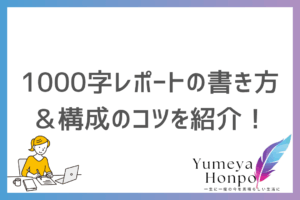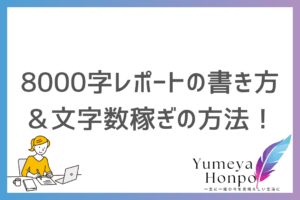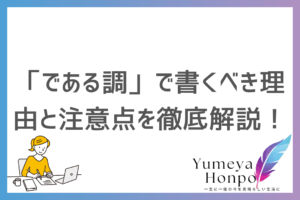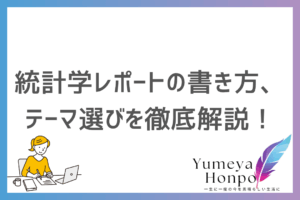「レポートの結論って何を書けばいいの?」
「結論の例文を知りたい」
「結論を書いても文字数が足りない」
レポートを書き進めて本論まで完成したのに、結論で何を書けばいいか分からず手が止まってしまう経験はありませんか。
「結論」の部分は、レポート全体の印象を決める重要な部分です。
この記事では、レポートの結論の書き方について、基本的な構成から書く際の注意点まで詳しく解説していきます。
結論がまとまらず、全体的にレポートを書き直したいという方はこちら
結論に書くべき3つの要素

レポートの結論を書く際は、以下の3つの要素を含めることで、まとまりのある文章になります。
1. 本論の要約
まず最初に、本論で述べた内容を簡潔にまとめます。
ただし、単純な繰り返しではなく、重要なポイントを取り上げて整理することが大切です。
例えば、3つの観点から分析した場合は、それぞれの要点を1〜2文でまとめ、全体として何が明らかになったかを示します。
2. 得られた気づきと考察
次に、レポートを通じて得られた新しい発見や理解を述べます。
ここでは以下のような内容を含めると効果的です。
- 調査や分析から分かったこと
- 当初の予想と異なった点
- 新たに気づいた問題点
- 自分の考えの変化や深まり
単なる感想ではなく、意味のある内容になるよう意識して考察をしましょう。
3. 今後の課題と展望
最後に、今回のレポートで扱えなかった点や、さらに研究すべき課題を提示します。
これにより、今後の追及すべき方向性が明確になり、不足しているポイントを次回補いやすくなります。
また、「本レポートを通じて」「以上の考察から」「今後の課題として」など、結論でよく使われる定型表現を覚えておくと、スムーズに書き始められます。
以上の内容を書くのが難しそうだったり、レポート全体の書き直しが必要だけど時間がないという方はレポート代行を利用してみてください。
分野別結論の書き方と例文

専攻分野によって、結論で重視すべきポイントが異なります。
今回は以下の分野での結論の書き方について紹介します。
- 文学
- 経済学
- 社会学
- 医学
- 法学
- 工学
文学系レポートの場合
文学系レポートでは、自分ならではの作品の見方や、時代背景との関連性が重視されます。
例: 「本レポートでは、明治時代の文学作品における女性像の変遷について考察した。西洋文化の影響を受けながらも、日本独自の価値観が残存していることが明らかになった。今後は、同時代の新聞や雑誌なども分析対象に加えることで、より包括的な女性観の変化を捉えることができるだろう。」
経済学系レポートの場合
経済学系では、データにきちんと根拠があるかどうかや、その結果からどんな提案ができるかが大事になります。
例: 「本レポートでは、最低賃金引き上げが雇用に与える影響について分析した。都道府県別のパネルデータを用いた結果、短期的には雇用への負の影響が確認されたが、長期的には生産性向上により相殺される可能性が示唆された。今後は、産業別の詳細な分析を行い、より精緻な政策提言につなげていく必要があるだろう。」
社会科学系レポートの場合
社会科学系では、現実社会へ利用できる可能性と、調査の限界を明確にすることが重要です。
例: 「本レポートでは、大学生のSNS利用と学業成績の相関について分析した。過度な利用は成績低下につながる傾向が見られたが、サンプル数が限定的であった。より大規模な調査を実施し、学年や専攻による違いも検討することで、効果的なSNS活用法の提案につながると考えられる。」
医学系レポートの場合
医学系では、その研究が医療に役立つかどうかと、人に関わる研究としてのマナーや配慮について述べるようにしましょう。
例: 「本レポートでは、糖尿病患者の生活習慣改善プログラムの効果について検討した。運動療法と食事指導の併用により、HbA1c値の有意な改善が認められた。ただし、対象者が外来患者に限定されており、重症例での効果は不明である。今後は入院患者も含めた幅広い症例での検証と、長期的な予後調査が必要となるだろう。」
法学系レポートの場合
法学系では、法律の解釈の正しさや、それが社会に与える影響を考えることが大切です。
例: 「本レポートでは、個人情報保護法改正による企業への影響について検討した。規制強化により企業の負担は増加するものの、消費者保護の観点からは必要な措置といえる。しかし、中小企業への配慮や国際的な規制との整合性など、課題も残されている。今後は、諸外国の法制度との比較研究を通じて、より実効性の高い制度設計を検討する必要があるだろう。」
工学系レポートの場合
工学系では、その技術が現実に使えるかどうかと、使うときに起こりそうな問題まで考察しましょう。
例: 「本レポートでは、AIを活用した交通渋滞予測システムの開発について検討した。機械学習モデルにより、80%以上の精度で渋滞を予測することができた。しかし、リアルタイムでの処理速度や、悪天候時の予測精度には課題が残る。実用化に向けては、計算処理の最適化と、多様な環境下でのデータ収集が不可欠である。」
結論を書く際の注意点

質の高い結論を書くために、以下の点に注意しましょう。
新しい論点を持ち出さない
結論で初めて登場する概念や議論は避けるべきです。
本論で触れていない内容を突然持ち出すと、レポート全体の一貫性が失われます。
もし新しい視点を加えたい場合は、本論に戻って追記することを検討しましょう。
単なる感想にしない
「勉強になりました」「難しかったです」といった個人的な感想は、レポートには不適切なので、このような表現は避けるようにしましょう。
個人的な感想ではなく、根拠に基づいた内容をしっかりと書くことが大切です。
謙虚になりすぎない
教授は、結論で学生の理解度や思考の深さを確認しています。
つまり、レポートを通じて何を学び、どのような視点を得たのかが問われているのです。
そのため、「力不足で十分な分析ができなかった」など、必要以上に謙遜する表現は避けましょう。
限界は認めつつも、達成できたことをしっかりと示すことが大切です。
結論と「終わりに」は一緒
結論と「終わりに」はレポートにおいてはほぼ同じなので、どちらを使っても大丈夫です。
ただしレポートの冒頭で、「初めに」を使っている場合は「終わりに」を、序論を使っている場合は結論を使うようにしましょう。
プロに依頼する

結論を書こうとしたら、自分のレポートが低クオリティーだと気がついたけど、書き直す時間がないという方は、レポート代行サービスの利用をオススメします。
夢屋本舗では、各分野の専門知識を持ったライターが、質の高いレポートを作成します。
結論だけでなく、レポート全体の構成から参考文献まで、全て作成をしてくれるため、確実に高品質なレポートが完成します。
特に以下のような場合におすすめです。
- 締切が迫っているが、まとまった時間が取れない
- 専門的な内容で、適切な結論が書けない
- 他の重要な課題や試験勉強を優先したい
まとめ
レポートの結論を書くためのポイントをまとめると、以下のようになります。
- 必須の3要素:本論の要約、考察、今後の課題
- 分野別の書き方と例文:文学、経済学、社会学、医学、法学、工学
- 注意点:新しい論点は持ち出さない、感想ではなく考察を書く、謙虚になりすぎない
結論は読み手に最後の印象を与える重要な部分です。
本論の内容をしっかりと踏まえながら、自分なりの考察と今後の展望を述べることで、完成度の高いレポートになります。
もし自分で書くのが難しい場合は、夢屋本舗のようなプロのレポート代行サービスを活用することで、時間を有効に使いながら質の高いレポートを提出することができます。